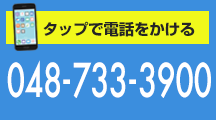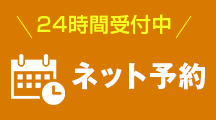月別アーカイブ
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年4月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年7月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
カテゴリ一覧
確か中等講座に入ってからだったと思うが、いよいよ背中の観察になった。
まずは背骨の観察。
頚椎、胸椎、腰椎の棘突起を実際に触って観察していく。
最初は頚椎6番から腰椎まで番号を数えて観察する
頚椎6.7番、胸椎1〜12番、腰椎1〜5番。
それから棘突起の状態を観察していく。
小さいもの、大きなもの、とんがってるもの、隣とくっついてるもの、全て意味がある。
また背骨自体が読みやすい人、読みにくい人がいる。
これも意味がある。
背骨が読みやすい人は若い人、素直な人。
読みにくい人は高齢者、自分の気持ちを出さない人。
確かに道場で何十人と練習すると読みやすい人は素直な人、読みにくい人は感情を表に出さない人というのが分かる気がする。
そして、私はよく
「高橋さんの背骨は分からないな〜。凄く難しいよ。」
と言われた。
うーむ、確かに私はあまり感情を表に出さないタイプだと思う。
野口整体、井本整体において、整体の目指すものとは何であろうか?
何のために整体をするのか?
一般的な治療院においての施術の目的は、疼痛緩和や疲労回復であろう。
それに対し、整体の目的は「整体」になることでる。
「整体」になる?何それ?って感じだが、
「整体」になるとは、日常生活での様々な刺激に対して柔軟に対応できる心身になることである。
例えば、ウィルスに感染したら熱を出し免疫力を上げウィルスを撃退できる体、悪いものを食べたら吐いたり下したりできる体、疲れたら素直に疲労を感じ回復できる体。
いわば自然治癒力が高い体になることであるともいえよう。
しかし、普通の人からするとなんで整体で自然治癒力が高まるの?と思うと思う。
体は疲労や普段の体の使い方の癖で、偏ってくる。
その偏りは、ある箇所の硬結になる。
硬結を取り体に響かせることができれば、その響きは体を変え偏りを矯正する。
例えば胃が悪い人は、胃の反応点に硬結を出す。
その硬結を正確に取り体に響かせれば、その響は胃にフィードバックし胃の働きを高める。
本来その人が持っている胃の働きが出てくる。
整体は病気治しではない。
体の本来持っている働きを高めるだけである。
野口整体、井本整体では
「熱を出す事は悪い事ではなく、むしろ身体がリフレッシュする良い事である。」
としている。
熱を出すというのは免疫力が盛んな証拠なのだ。
実際、子供などは風邪を引いても高熱を出してすぐに治ってしまうが、高齢になると熱は出ないが、いつまで風邪が治らないでいる。
なので、整体道場では
「俺、こないだ38度の熱が出たんだよ。」
「いいな〜。俺なんか最近熱が出ないんだよ。」
みたいな会話をしている。
私も一度、高熱を出して頑固な膝痛が治った経験がある。
膝を痛めたのは、整体のゴールデンウィークの特別講義でのこと。
特別講義3日間、ほぼ正座していて痛くなった。
特別講義は、朝から夜まで行われたが、その時の特別講義は操法も正座で受けることが多かった。
話を聞く座学も正座で聞く。
3日間、正座しっぱなしで特別講義が終わって少ししたら膝が痛くてしゃがめなくなってしまった。
正座も人によっては何ともないが、私は苦手であった。
正座については整体に入門した当初、先輩から
「そのうち慣れるから大丈夫だよ。」
と言われたが、結局辞めるまで慣れなかった。
そんな慣れない正座を3日間ずっとしていたので、しゃがめないほどに痛くなり、整骨院での仕事の際にも痛みがあった。
整骨院で鍼灸やいろいろ治療したが、完璧には痛みは取れず8月はまだ痛いままであった。
そして、8月のお盆前、外因不明の38度の高熱が出た。
別に風邪を引いたわけでもなく、熱だけが急にでた感じで、それが2日ほど続いた。
整体では熱が出たら解熱剤は飲まないで、熱は出し切った方が良いとされているので、解熱剤は飲まないでいた。
それから熱が下がると、やく3ヶ月ほど痛かった膝がすっかり治っていた。痛みが全くなくなっていた。
それ以来、今まで痛くなったことはない。
整体でいう「熱は身体の大掃除」を自らの身体で体験した。
井本整体に通い出して何ヶ月か経つと顔馴染みも増えてきて、同期や先輩の素性も分かってきた。
当時の道場生は、柔道整復師、鍼灸マッサージ師、理学療法士、助産師、薬剤師、整体師などの医療系の人から、サラリーマン、主婦、フリーターなど様々な人が整体を学びに来ていた。
そして道場に入ってしまえば、医療資格は関係なく入門した順に先輩、後輩である。
私は井本整体に入門した時、すでに開業していて業界歴は15年ほどであったが、道場では半年前に入った素人でも先輩であり、その人から技術の指摘を受けていた。
私は普段、整骨院で患者さんから施術の指摘されることはないので、素人の先輩の厳しい指摘も一般の人の意見としてありがたく聞いていた。
道場ではペアになり練習することは前述したが、慣れてくると相性のいい先輩と悪い先輩がいることが分かった。
それは体の問題かもしれないし、性格の問題かもしれない。
私は比較的誰とでも良好な関係を築いていたが、それでも苦手な人は数人いた。
中に薬学部の年配の教授も整体を学びに来ていたが、なぜかこの人とは相性が悪く、この人と組むと上手くできなかった。
「全然取れてませーん」
「呼吸の誘導ができてませーん」
など言われ、そのうちにはやる前から、この人には無理だと思うようになった。
また、超過敏な先輩もいて手を触れただけで
「その触り方だめ。呼吸が苦しくなる。」
と言う人もいて、そういう人は苦手であった。
もちろん先輩の操法も受けるので、上手い先輩や下手な先輩もいた。
認定指導者の先輩と組む時も多々あったが、認定指導者の先輩はさすが素晴らしい技術を持っていた。
達人の先輩と組むと、観察している手が既に気持ちいい。
観察されたかと思うと、つかさず操法に入る。
的確に硬結を捉えられたかと思うと、呼吸を入れる間も無く次の硬結を捉えていく。的確に次々と硬結を捉えられるとなんともいえない快感がある。
何回か書いたが、上手いは人ほど技術が早い。下手な人ほど遅い。
整体の究極は呼吸の誘導である。
術者の意のままに受け手の呼吸を操る。
緊張と弛緩。
「間」伸びした技術は、間抜けなのだろう。
「機」「度」「間」
操法の要諦はこれに集約される。
整体においては「型、構え」は基本にして最重要ポイントである。
「型、構え」とは、操法するときのフォームである。
例えば武道では型、構えをまず最初に習うが、整体も同じである。
相手とのポジション、呼吸の間、着手のタイミング、手を当てる位置、手の使い方、力の流し方など完璧になるまで練習する。
そして整体道場にある程度通うようになると、型、構えを見ただけで術者の熟達度がわかるようになる。
見ていて「決まっている!」と見える人は硬結を取れている。逆に「決まってない」と見える人は硬硬を捉えてない。
型、構えができていないと正しい硬結を捉えることができないのだ。
逆に型、構えがしっかりできていれば、硬結は自然と親指の下に当たってくるという。
井本整体では型、構えの練習で「手の三里」の硬結を取る練習がある。
整体の「手の三里」は腕(前腕伸筋群)にあるのツボを使い、その硬結をとり、体全体に響かせる技術である。
単にその場所を押さえれば良いというものではなく、相手とのポジション、呼吸の間、自分の体の使い方、正しいツボの位置、正しい手の使い方ができてないと体全体には響かない。
練習では「手の三里」だけで2時間以上練習し、その場所が内出血を起こしたこともあった。
「型、構え」は繰り返し練習して体に覚えこませやっと習得できるものだと思う。
整体道場では先輩と組になり練習するのが、厳しい先輩にはまだ手を触れる前、座って、さあやろう!とする時に「はい、やり直し。」と言われることもあった。
座る位置、構えができていないのだ。
これは経験を積むと分かるようになるが、上手い人と組むと座って構えられた瞬間に「来る!」と感じる。
そしてもっと感性が高まるともっと凄いのだが、それは後で別に書きます。
素人は触って説明されても取れない硬結が、達人になると人が練習しているのをみて硬結を取るのを誘導できるようになる。
もっと凄くなると見なくても感じるようになる。
そして型、構えができると、操法を何時間やっても疲れない。
よくマッサージをやって「疲れた〜」と言う施術者がいるが、その人は基本ができてないのである。
正しいフォームで行えば何時間マッサージしても疲れない。
施術で疲れてるうちは三流であり、その効果も三流である。
正しく硬結を響かせるには、術者が脱力してなければならない。術者が力んで力で押していると、受け手の表層筋も緊張して中には響かない。
これは2006年から2011年の約5年間、私が34歳から38歳の頃、整骨院を開業して6年ほど経った頃の話である。この5年間は1年で正月の3日間しか休まず整骨院をやりながら週2日、日曜祭日、全て整体に通っていた。整体狂時代である。
井本整体では最初の3カ月間は主にお腹の操法を学ぶ。
たぶんこれほどお腹に時間をかけて深く学ぶところは他に無いと思う。
お腹について、まずはざっくりと
「良いお腹、良くないお腹」とはどういうお腹だろうか?
良いお腹とは
おへそを中心に集まった弾力のあるお腹である。
腸の働きが良く蠕動運動が盛んなお腹である。
疲れたお腹とは
おへそが凹み弾力の無くなったお腹である。
腸の働きが悪く緩みすぎて弾力のないお腹である。
実際にお腹に手を当てた時に、真ん中が盛り上がっているお腹は良いお腹であり、くぼんで舟床状になっているお腹は疲れたお腹なのだ。
整体では自然治癒力のある体を「潜在体力のある体」と言う。
潜在体力が現れる箇所はいくつかあるが、お腹も潜在体力が現れる箇所である。
一見健康そうに見えても潜在体力のない体は一度崩れるともろい。
潜在体力のある体は多少病気しても回復が早い。
そんな潜在体力が顕著に現れる箇所の一つがお腹である。
整体で最初に腹部から学ぶのは、呼吸を感じる訓練、圧度の訓練などもあるが、特に腹部は丁寧に触れなければならない箇所なので体の基本的な触れ方を学ぶのに最適な箇所なのだろう。
これは2006年から2011年の約5年間、私が34歳から38歳の頃、整骨院を開業して6年ほど経った頃の話である。この5年間は1年で正月の3日間しか休まず整骨院をやりながら週2日、日曜祭日、全て整体に通っていた。整体狂時代の話である。
井本整体では最初に『命への礼』を教わる。
『命への礼』とは何ぞや?
井本整体では、実技練習の前に人の体に触れる心構えとして「命への礼」を教わる。
『命への礼』とは「生命の尊厳を認識し相手を尊重しなさい」ということだ。
例え練習といえど、相手の体、命を借りて練習させて頂くのである。
相手への感謝、礼儀を欠いてはいけないという教えである。
前回書いたが、私は初日に先輩から
「あなたは人を物扱いしてます。もっと丁寧に慎重に触らなくてはダメです。」
と忠告された。
根が鈍感なせいかそれほど気にしなかったが、初日なので少し面食らった。
私は整骨院で1日中、人の体に触れている。
いわば慣れている。慣れ過ぎている。
慣れすぎていた為、無意識に雑に触れていたのかもしれない。
しかし、考えると「命の尊厳への意識」は本来あるべき医療業界こそ低いのではないか?
仕事になると患者さんが次から次である。
いちいち生命へ尊厳など気にしている暇はない。
中にはワガママな人、神経質な人もいる。
「このヤロー!」と思う時もある。
しかし、それでも生命の尊厳『命への礼』は忘れてはならない。
鍼灸学校、柔整学校でもこういうことは教わらない。
今まで会った治療家を振り返ると『命への礼』がある治療家、ない治療家がいる。
治療家として名のある人は「命への礼」があるようにと思う。
それは、患者さんは感じるものだ。
井本整体に行ってなんとなく感じていた大切なことに気付くことができた気がする。
これは2006年から2011年の約5年間、私が34歳から38歳の頃、整骨院を開業して6年ほど経った頃の話である。
井本整体の初等講座、最初は毎週日曜に行った。
(途中から水曜にH先生の初等講座もあったので、水、日曜で行くようになった。初めはどちらかしか出席できないものと思っていたが、両方出席しても良いシステムなのが分かり両方出席した。)
日曜、初等講座に参加した初日。
前述したが、初等講座の初めの三ヶ月は「腹部一二調律点」であり腹部の施術を主に行った。
講座は、最初20〜30分ほどの座学があり、それから実技練習に入る。
実技練習は2人組になり、お互いに実技を行い感想を言いあう。終了すると手を挙げて、他の終わった組と入れ替えをして再び練習する。
初等講座に参加していたのは60〜80人ほどいたが、その生徒の8割は先輩であった。
井本整体では一度受講した講座は何回でも出ても良く、生徒は何度も受講して技術を高めるシステムになっている。
そこが学校ではなく道場なのだ。
武術と同じで繰り返し練習することで体感で会得していく技術なのだ。
基本的に初めての生徒は先輩と組み、指導してもらう。
初日、私も何人かの先輩と組み練習させて頂いた。
しかし、ある一人の先輩から
「あなたは人を物扱いしてます。触り方が雑過ぎます。もっと丁寧に優しく触らないとダメです。」
と、厳しいことを言われた。
(えっ!物扱い?どういうこと?)
「はあ、すいません。」
とだけ言った。
根が鈍感なのでたいして気にしなかったが、初日ということもあり少し面食らった。
これは今だから言えるが、人に触った事がない素人は最初は緊張して慎重に触る。
先輩は新人だと思っていたが、妙に慣れて雑に触るものだから厳しく言ったのだろう。ちなみにその先輩はその後もっと厳しい先輩がいる中、優しい先輩であった。
私は整骨院では1日中、1日8時間ほど人の体を触っている。慣れているというか、慣れすぎている。当時の私はそこに雑さもあったのだと思う。
「触診の丁寧さ」
これは、井本整体で身につけた技術の一つである。
井本整体を卒業してからいくつかの勉強会に行ったが、どこに行っても実技になると
「高橋さん、上手いですね。」
と言われる。
治療家の実力は触られた瞬間に分かる。
触り方で「この人はやるな!」とか「この人は下手だな。」とか分かる。
井本整体では着手(手を触れる瞬間)を大事にする。
着手には、触れる箇所、タイミング(呼吸の間)、圧度などが重要になる。
訓練された治療家は、それらを考えないで行う。
意識しないで「手」が勝手に相手の欲しい箇所に行くのである。ふっと手を置いた箇所に「硬結」があるのである。
そういう練習を整体では行う。
私も井本整体に入る前に臨床を15年ほどやっていたが、経験上、これはそういう練習をしないとできない。
ただ長く臨床をやっているだけでは、雑な治療家は雑なままである。
これは2006年から2011年の約5年間、私が34歳から38歳の頃、整骨院を開業して6年ほど経った頃の話である。
初めて井本整体の道場を訪れたのは4月の下旬の日曜日であった。
東京の千駄ヶ谷は埼玉の春日部から1時間ほどで着いた。
井本整体は千駄ヶ谷駅からは徒歩10分ほどであった。木の立派な看板に「井本整体」と書かれていたので、住宅街の中にあったがすぐに分かった。
中に入ると1階は井本先生の操法室(施術室)であり、2階が整体道場になっていた。
ちなみに地下は談話室になっており食事をしたり休憩する場所で、4階は自主練の部屋と、認定指導者の会議室のようであった。
中に入ると受付で体験申し込みをして2階の道場に通された。
講義の開始が10時からだったので少し早めに行ったのだが、すでに他の生徒達は来ているようで、ざっと60〜80人ほどいた。
また道場の広さも学校の教室3つ分、別の言い方だと柔道の試合2面分くらいの広さがあり、その規模に圧倒されてしまった。
(ここでどんな講義が行われているのだろう。)
正座して待ちながら、なんだかわくわくしていた。
井本整体の練習はベットではなく床で行われる。
講義は正座で聞き、操法の練習は床に受け手が寝て行われる。
講義が始まる前、講師のF先生に
「何が療術やってますか?」
と聞かれたが
(療術って何?)
「やってません。」
と答えてしまったが、後で分かったが療術とは整体の昔の言い方であり、野口整体全盛の時代は療術と言っていたそうだ。
初日はベテランの先輩が専属で付いてくれ、初めから教えてくれた。
初等講座の最初三ヶ月は腹部一二調律点であった。
約3ヶ月、主に腹部の練習するのである。
もちろん腹部は鍼灸学校でも教わったが、実際に腹部を時間をかけて触るのは初めてであった。
今思えば。井本整体ほど真剣に丁寧に体を観察するところは他に無いと思う。
それは野口整体から引き継いだものだろう。
野口整体では、昔はパンツ1枚になり1日中、夜を明かしてお互い観察したそうだ。
さすがに井本整体ではパンツ1枚になり練習する事はなかったが、特別講義の時は朝から夜まで講義、夜も終電近くまで自主練があったときもあった。
初めて井本整体を体験をしてみて、道場生の真剣な練習風景、講師のF先生の深みのある講義に好感が持てた。
また道場の「凛」とした雰囲気も気持ちよくとりあえず初等講座を受けることにした。
これは2006年から2011年の約5年間、私が34歳から38歳の頃、整骨院を開業して6年ほど経った頃の話である。
この約5年間は整骨院を開業しながら、整体道場に週2回通い勉強した。1年の休みは大晦日、元旦、2日の約3日しか取らず全ての休日を整体道場に通った。
我ながらよく通ったなと思うが、通い始めた2006年は長女が生まれた年であった。子煩悩なパパなら、子供と一緒にいるのが幸せなのだろう。私ももちろん子供は可愛い。しかし、それから5年間はほぼ全ての休日は整体勉強に通う整体狂時代だった。
そもそも何故、整体研修に行くようになったかというと、妻が「マッサージの資格を取りたい!」と言い出したのがきっかけであった。
マッサージの国家資格は3年間学校に通わなければならない。時間もお金もかかる。
「とりあえず民間資格の整体いいんじゃない?」ということで、いろいろな整体や民間資格を調べ始めた。
いろいろ調べていると妻より私の方が興味が出てきて、私がいくつかのスクールの体験に行ってみた。
スクールに行ってみると、ほとんどのスクールは素人相手のものであった。
ある整体は、やっている技術はカイロプラクティックなのに何故か理論は東洋医学。しかも東洋医学もデタラメ。
また、あるところはお金の話に終始して肝心の技術、理論はほぼなく、痛いところをただ押すだけだったりした。
そんな折、本屋で治療系の本をパラパラ見ていると、1冊だけ「この人は本物かも?」と思える本を見つけた。
「この著者はどんな人なんだろう?」と経歴を見てみると、
「あっ!あー。。。そうか。。」納得した。
私の鍼の師が
「整体とかカイロとはほとんどはくだらないものだが、野口整体だけは本物だぞ。時間があったら勉強してみるといいぞ。」
と言っていたのを思い出した。
その本の著者は、子供の頃より野口整体の支部長をしていた父に整体の英才教育をされた先生であった。
その本を購入し熟読したが、読めば読むほど「この人は本物だ。」という確信が持てた。
数日後、実際にそこに行って体験してみたい!という気持ちが強くなり、そこの整体に電話をして実際行くことになった。
ここまで読んで、あれ?奥さんが整体行くんじゃなかったの?と思われると思うが、妻は結局、鍼灸マッサージの国家資格を取る方がいいという結論になり、数年後、子育てをしながら専門学校に通い国家資格を取った。
それから数日後、確か4月の下旬の日曜日。
私は東京千駄ヶ谷の「井本整体」の整体道場を初めて訪れるのであった。